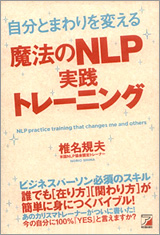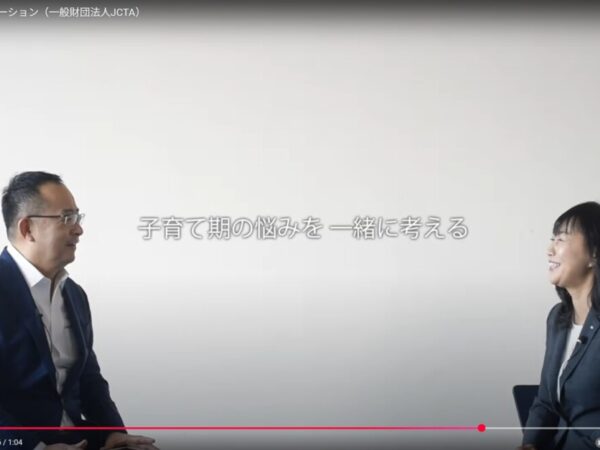お客様のための仕事が顧客を遠ざける
あるお客様が新聞用(近くを見る)メガネの修理で、ホームセンター内の眼鏡売り場に行った。
店員Aは、そのお客様のメガネの修理ができないので、それを購入したお店で修理をするようにアドバイスをした。
店員Bは、お客様が新聞が読めるようにと、修理は出来ないので、店内にある他のメガネを購入することを提案した。
店員Cは、お客様が購入した他店に連絡を取り、お客様にかわって修理を依頼してくれた。さらに、それまで新聞を読むのに困るだろうと思って、代替品を無料で貸した。(通常、無料で貸し出すなんてサービスを行っていない)
お客様にとって、スタッフCの行動が期待を超えるけれど、これではコスト倒れもいいところになる。
スタッフBは、少し押し売りか。すると、スタッフAの選択が経営者側からすると望まれることなのか?
「いやいや、スタッフCが正解だ。小さな仕事から、お付き合いは一生だ」とある成長を続ける社長は言うかも知れない。私もちょっと賛成。だって、お客様が満足するだろう。
さて、本当の問題は、無料で代替品を借りたお客様が、それを誰かに話をしたとする。そして、それを聞いた別の客が同じように新聞が読めない状態になり、眼鏡屋に行ったときスタッフBに担当され、別の眼鏡の購入を迫られたときだ。
無料の貸し出しを期待していたお客は、憤慨するのではないか。
「俺には、無料で貸さないのか!」
なるほど、スタッフA、B、C。それぞれ、お客の為、会社の為に仕事をしている。では、どこに問題があるのか。
普遍の想いが決まっていない
「トップマネジメントが、この問いについて徹底的に検討を行い、答えを出しておかなければ、上から下にいたるあらゆる階層の者が、それぞれ相異なる両立不能な矛盾 した事業の定義に従って決定を行い、行動することになる。互いの違いに気付くこと なく、反対方向に向かって努力を続ける。あるいは揃って間違った定義に従い、間違っ た決定を行い、間違った行動をする」
(『マネジメント』 P.F.ドラッカー)
社長を含め、全社員で『普遍の想い』である使命が明確でないから起こるトラブルだ。
徹底的に話し合い、「これでいこう」という考えをはっきりさせなければ、お互いの考えの違いに気がつかないまま、それぞれが異なる定規で仕事にすることになる。
働く者は、整理されない考えを頭の中に残しながら、自分の判断で行動をするようになる。目に見えない問題は取り上げられず、目に見える問題に振り回される。
大切なことだ。使命(私たちの事業)の定義を曖昧にしておけば、必ず、事業は迷走する。時代の潮流に飲み込まれ、事業は成長する力を失い、やがて事業の混迷が現実になる。
努力は嘘をつかないという。しかし、現場で働く者が、反対方向に向かって努力をすれば、反対方向に進む。努力するほど、現場での不調和が起こる。何のための努力なのか?
オンライン無償相談はこちらから https://www.mdinc.jp/tool/request/index.php?cid=1&tid=40
新規客が自然に集まる仕組みはこちらから https://www.mdinc.jp/tool_consultation/
広告・SNSに頼らない集客はこちらから https://www.mdinc.jp/webmarketing-toolconsulting/